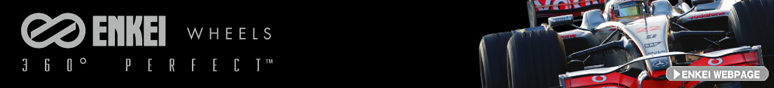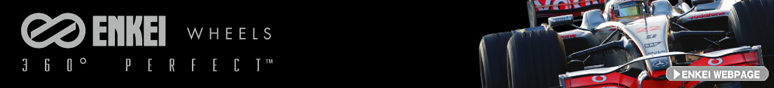|
マンガ“サーキットの狼”とともに'70年代に巻き起こったスーパーカーブーム。
子供たちを中心に社会現象となるほどの熱狂だった。
それから約10年後、'80年代の終わりに訪れたバブル期に
再びスーパーカーブームが起こる。
これは子供たちのヒーローではなく実際の購入対象・投機対象という色合いが濃く、
バブルの崩壊とともにブームも終焉を迎える。
この一次、二次を経て、現在は第三次スーパーカーブームを迎えている。
こうしたスーパーカーをメインに扱う雑誌として'97年に誕生した「ROSSO」。
今回はその三代目編集長・平井大介氏にお話をうかがった。
スーパーカー四天王。
現在、多くのスーパーカーが存在しますが、フェラーリ、ランボルギーニ、ポルシェ、これに最近はアストンマーティンを加えて便宜上スーパーカー四天王と呼んでいます。フェラーリとランボルギーニは象徴的なスーパーカー、ポルシェは乗って驚く動力性能が魅力。アストンマーティンはこうしたスーパーカーとは違う魅力があります。スーパーカーの多くは乗る側にそれなりの気構えや力を要求するんですが、アストンマーティンは高級GTカーの魅力で、例えば女性をエスコートする大人の男の魅力(笑)。内装の色使いや落ち着きに英国の伝統を感じますね。
四天王以外にも魅力を感じるクルマはあります。例えばマセラティ。エンジンがフェラーリということもありますが、アクセルを踏むともう脳がとろけそう(笑)。加速の仕方やスピードの出方が官能的なんです。その他イタリアのパガーニ、日本の光岡など小規模な生産でスーパーカーを生み出しているメーカーもありますし、現在では大メーカーもこの市場の魅力に気づいて参入してきている状況がありますね。フォルクスワーゲンのような巨大メーカーもブガッティとしてスーパーカーを作っていますし。
どんなクルマが熱い思いにさせてくれるか。今、メーカーもオーナーもそれぞれにスーパーカーを見つけて育てています。それがこの第三次スーパーカー時代を作っているんだと思います。
究極を突き抜けて進化。
僕は35才になりますが、30年前に第一次スーパーカーブームの洗礼を受けた子供でした。その頃のスーパーカー少年のアイドルはやはりカウンタックや512BB。3歳頃からミニカーを集め、街道を行く車の名前を当てて楽しむような子供で、小学校の卒業文集にはすでに「将来は車関係の仕事に」と書いてましたね(笑)。クルマ雑誌の編集という仕事を知ったのは車雑誌を読み始めた中学時代です。
そんなでしたから、大学での就職活動もやはりクルマ関係ばかり。カーディーラーはもちろん「毎日車の運転ができる」とタクシー運転手まで検討しましたが(笑)、縁があって今の会社に新卒で入社することができ、夢がかなったといえますね。最初は広告部に配属、その後カーマガジン編集部を経て、イタリア車好きを買われたのか'99年からROSSO編集部に入りました。最初に担当したのがランボルギーニなどの歴史モノ。これが楽しくて、スーパーカー少年の頃の心が蘇ってその魅力を再認識しましたね。
取材で最新のスーパーカーと出会いますが、いつも「もう究極なのでは」「もうこれを越えられないだろう」と思うんです。ですから次の新型では「まあそれほど進化していないだろう」と思って行ってみると、予測を二倍も越えるような驚きに出会うんですよ。例えば最新のフェラーリ430スクーデリアもそんな一台でした。パドルシフトなんかはもう、2〜3年前のF1のパドルスピードと変わらないで切り替わるんです。F1のバーチャル体験が安全にできるという感覚ですよ(笑)。フェラーリは特に市販車がレースのノウハウをフィードバックして驚く程成長し続けています。
スーパーカーは常に限界や究極を無限に広げて行く世界なので、常に驚きがあり、そこに大きな魅力があるんですね。まだまだスーパーになってゆくのを実感しています。
情報の“質”で勝負。
今、雑誌は情報の“即時性”という点でインターネットにかないません。ではどこで勝負するか。それは情報の“質の高さ”だと考えています。現場でリアルに「スゴイ!」と感じたものを現場感を持って伝えるインプレッション、そして“この写真1枚のためにこの本を買ってもいい”と思っていただけるくらい美しい写真。そういった事を最も大切にして編集しています。確かに乗車したときの官能的な感覚を伝えるのは難しいし、最近のクルマはボディラインが複雑なので写真を撮るのもなかなか難しいんです。でも、読者がいつまでも大切に持っていたくなるようなページを1ページでも多く作りたい。それが雑誌の生命線だと思って努力しています。
ROSSOはスーパーカー専門誌といわれますけど、僕自身はそう思っていないんですよ(笑)。もちろんスーパーカーがメインコンテンツですが、そこを中心にもう少し幅を広く考えています。それ以外にもあるスーパーなクルマやモノ、ガレージやグッズなども含めて、クルマを楽しむその他の要素についても注目して情報提供をしていきたいと思っています。(以下次号)
 |
|
平井 大介(ひらい・だいすけ)
1975年 千葉県生まれ |
|
千葉県松戸市出身。大学卒業後、株式会社ネコ・パブリッシング広告部に入社、カーマガジン編集部に異動し編集者としての仕事をスタート。'97年発刊のROSSOに'99年より異動、副編集長を務め、昨年12月に編集長に就任。
http://www.rosso-mag.com/ |
|